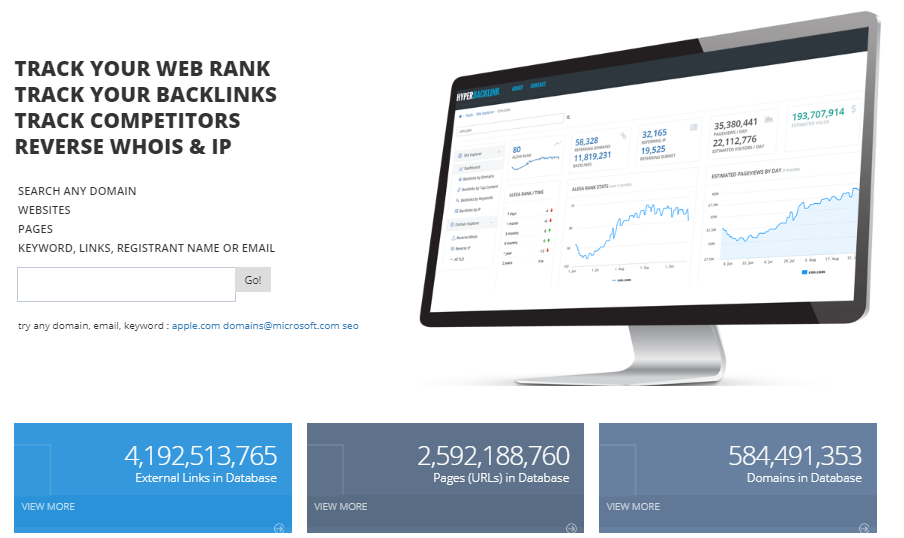こんにちは。
ライフウォーカーyamadaです。
今回は、各地里山を取材させていただいた中で、特にジビエの取り組み、野生鳥獣との共存、有害鳥獣対策について記したいと思います。
ジビエブームの裏側
ブーム、と呼ばれるようになって久しいジビエ。
ジビエという言葉自体、とても一般的になってきたと思う。
テレビ番組等メディアで取り上げられるが増えた。
象徴的なこととして、ぐるなびで毎年発表される「今年の一皿」で2014年に「ジビエ料理」が選ばれたことがある。
ジビエといえば高級なイメージだが、
JR東日本では系列のレストランではシカ肉のハンバーガーが販売されるなど、確実に身近になっている。
これには、日本ジビエ振興協議会、その代表を務める藤木シェフや、長野県や狩猟者の方々などの尽力がある。
そして、高知県といえばカツオ。
そんな高知県でも、あらゆる料理が競いあうイベントでもジビエ料理がナンバーワンになったそう。
ジビエは注目の的だ。
狩猟者、処理業者、レストランや加工業者、自治体、国など様々な立場の方々がジビエ振興のために努力されてきたことがある。
そして都市に住んでいるとわかりにくいことだが、ジビエが振興される根幹には、深刻な農作物被害がある。
ジビエ振興は純粋にビジネスではない。
ジビエブームは、農業、農山村を守ることが根底にある。
有害鳥獣による野作網被害の現状

有害鳥獣による農作物被害額(平成28年度)は172億円(前年比で3%減少)。
それに対し、農業産出額は2兆2,025億円だから、約1%弱が野生鳥獣に食べられていることになる。
1%、というと少なく感じるかもしれないが、有害鳥獣被害は被害額だけでは語れない。
被害の中には、単に果物が食べられた、野菜が食べられた、だけでは済まされないからだ。
有害鳥獣は、ブドウやミカンの樹木自体を損傷させたり、田んぼの畔や段々畑の石垣を壊す、ため池ののり面を掘り起こし決壊や漏水を引き起こす、といったことがある。
桃栗三年柿八年、というように、果樹の樹体を育てるのには時間がかかる。農家にとって果樹は10年、20年かけて育てる「資産」だ。有害獣は農家の資産を破壊する。
ため池は農業用水を確保する大切な施設だが、それが決壊するとなると水田営農ができなくなるどころから、住宅が浸水する、人的被害にもなる。
そして、収穫目前の米や野菜が一夜にしてイノシシやシカに食い荒らさられる…経済的被害はもちろんだが、精神的被害も計り知れない。
同じようなこととして、台風によってリンゴがすべて落ちしてしまう、豪雨でジャガイモが全部ダメになる、ということも起こりうるが、
精神的なダメージは、イノシシなどにやられるほうが大きい。
営農意欲をこれでもかと奪う。
台風は今年来ても、来年は来ないかもしれない。この被害は毎年ではない、と思える。
しかし、野生鳥獣は違う。一度、味と場所を覚えると、毎年必ず来る。
若い農家ならまだいいかもしれない。
労力をかけても防護柵をはろう、狩猟免許も取って自ら駆除してやる。とも思える。
だが、高齢で後継者もいない農家では、鳥獣被害が出始めた畑から、営農をやめていくことが少なくない。
被害がなければまだやれるのに。
地方の農業を支えているのは70代以上だ。
だから60代で定年して専業農家になったらまだ「若手」。
農家が営農をやめる…当のご本人はもちろん、この経済的損失は大きい。
地方は農業周辺の経済が多々ある。
農家は、種苗、肥料、たい肥、農薬、マルチングフィルム、トラクター、その燃料など様々な農業資材・農業機械を扱う。
地方ではそれらを販売・メンテナンスすることで生計を立てる業者、また農産物を流通業者、直売所など、農業を核として成り立つ事業が多々ある。それらに従事する方々がいる。
もちろん農家の減少は、大手の農薬メーカー、農機メーカーにも影響する。
農協も、農産物の手数料等により運営される。
農協職員として生活する方も当然いらっしゃるわけで、農家が1戸引退する、ということが経済に与える影響は大きい。
だから、有害鳥獣による農作物被害は、「〇年度は〇億円でした。」という金額だけでは済まされない。
その水面下の被害額はもっと大きい。
そして、有害鳥獣の防除は簡単ではない。
イノシシは賢い。そしてサルの対策はもっと難しい。
「サルが出始めたら、もう終わり」
それでも、
「シカやイノシシ等による農作物被害が深刻」
と言われても、都市に居て、農業に関わることがなければあまりピンとこないかもしれない。
しかし、これは全国民に関係することだと思う。
日本国内に居住し、食物を食べるかぎりは。
それは、農業は、単に農産物を生産する産業ではないと思うからだ。
食糧生産は安全保障上の問題になりうる。
有事の際、食糧が輸入されなくなったら国内生産で賄うしかない。
原油とは違い、野菜は備蓄できない。
田畑は、国内農業の生産力。
一度失われ、荒野と化した田畑を取り戻すのは難しい。
しかも、それ担う「人」も失われるのだから。
この平和な世だと想像できないけれど、私たちの子供、孫の代はわからない。
農家に、お願いですから野菜を分けてくださいと懇願しないといけないかもしれない。
農地は、農家の私有地だけれど、国民にとっても安全保障上の基盤。
農家にそれを守ってもらっているのだと思う。
有害鳥獣対策・ジビエ振興に税金を投じる是非
国、自治体はそこに税金を投じて有害鳥獣対策を行う。
国だけでも毎年100億円を超える税金が有害鳥獣対策に使われる。
全国の都道府県、市町村でもそれぞれ有害鳥獣対策費用に税金が投じられる。
そして、有害鳥獣対策に関わる国、県、市町村職員の人件費は、また別にかかる。
税金の直接的な使い道として、有害鳥獣の駆除、防護柵の整備などがある。
例えば、国はイノシシやシカの成獣1頭につき捕獲経費助成金として7000円または9000円(※)、
市町村は自治体によって異なるが、例えばイノシシやシカ一頭につき10,000円の捕獲奨励金支給している。
この場合、狩猟者はイノシシ成獣1頭を捕獲するたびに17000円などの捕獲経費などを受け取ることができる(自治体や猟友会、捕獲時期により扱いが異なります)。
※獣肉処理施設に搬入する場合は9000円以内にアップする仕組み。ジビエへの利用を促す意図がある。
防護柵は畑の周囲を金属柵や電気牧柵で囲むもの。
条件は厳しいが100%国のお金で鉄筋柵など資材を購入することができる。
農家が鳥獣被害により田畑を放棄すると、数年で荒廃し時がたつほど農地への復旧が困難になる。
耕作放棄地は野生鳥獣の住処にもなる。
農山村から人が減ること、耕作放棄地が増えることで、田畑と野生鳥獣の距離が近くなる悪循環。
一方、野生鳥獣は倍々ゲームで増える。
シカは年に1産、通常1頭の子を産むがそれでも生存個体数の3割を捕獲し続けないと、数は減少しないと聞く。
シカはつい最近までメスの狩猟が禁止されるなど、保護されてきた。
個体数管理に移行するのが遅かった。
一度に5頭も6頭も産むイノシシはもっと増える。
イノシシ、シカに、基本的に天敵はいない。
雪深い地域では、雪が多い年はわずかに個体淘汰があるようだ。
しかし、基本的に人間が捕獲し個体数管理していくかない。
イノシシ、シカを捕獲し、ジビエとし販売してビジネスになれば理想である。
もちろん、関係者たちはそれを目指している。
ただ、捕獲奨励金なしでは捕獲は進まない。
純粋にジビエの販売額だけでは狩猟者の捕獲経費・人件費を賄うのは無理だろう。狩猟者のボランティアになる。
狩猟免許の取得、狩猟税等税金、銃の維持、山へ入り、捕獲、捕獲中の搬出、処理施設の持ち込み、と手間・コストがかかる。
何日も駆けずり回ってやっと1頭とれたりする。
それで運よく獲れたシカの立派な成獣が50㎏あったとする。内臓、皮、骨など除くとその内精肉になるのは20㎏などと減少する。
平均単価キロ3000円として1頭の売り上げは6万円。そこに販管費、獣肉処理施設の運営費、償却費、処理者の人件費などがかかる。狩猟者に支払える買取額はごくわずかだ。
しかも、野生獣だから、個体差が大きい。捕獲できたからと言って肉にできるとは限らない。処理施設に持ち込んだ段階でNGだったり、さばいてみたがやっぱり肉にならない、ということが多々ある。
ジビエは効率が悪い。
飼育された牛・豚・鶏が、低コスト・低労力・一定の品質で生産されるのとはわけが違う。
(そんな牛・豚・鶏の畜産業だって補助金無しでは経営は困難だ)
だから、今でも捕獲された有害鳥獣のほとんどは埋設処分される。
シカ、イノシシでも肉になるのは一部だし、ハクビシン、アナグマ、アライグマ、カラスなど基本的に処分だ。
狩猟者が自分の山に穴を掘って埋める。そのまま放置することは禁止されている。
自治体によっては、捕獲奨励金の支払いの捕獲確認のために、市町村役場まで捕獲鳥獣を一旦持っていく必要がある。奨励金の支払いを厳格にするため。
なので、狩猟者は肉にならないから埋設するつもりの捕獲獣でも、いったん山から搬出し、役場で確認、また山にあげて埋設する、といった重労働がある。
狩猟者の年齢層も、農家とほぼイコール。高齢の狩猟者が地方の田畑・山林の守り手である。
狩猟者が少ない、またはいない地域では、農家自ら狩猟免許を取得し、駆除にも当たる必要がある。
農業だけでも人手足りない中、駆除もやらなければならない。
そして、
増ええすぎたイノシシ等は町中にも現れる。
毎年のようにイノシシに襲われ亡くなる方がいる。人的被害にもつながる。
津波など水害対策として防波堤、堤防に税金が投じられるように、有害鳥獣対策に税金が投じられるのは妥当だと思う。
ジビエを食べる意味
私たちがジビエを食べれば、間接的に有害獣対策を応援することになる。
狩猟者、農家を応援することもなる。
確かにクセは少しあるかもしれない。
だが、現在の処理技術は高くなっている、と思う。
現状、ネットで通販しているような処理施設のイノシシ肉、シカ肉であれば、期待してよいと思う。
楽天、アマゾンなどレビューを参照しながら購入すればほぼ大丈夫であろう。
本当にきれいに処理されるので、全くにおいがない。
個人的には、多少は獣肉特有の香りがあるほうが好きだ。
野性味を楽しみたい、と思う。
ジビエは高価?
ジビエは高級と表現したが、現状、ジビエは国産牛に比べると手頃だったりする。
例えば国産牛は細切れでも500円/100gだったりするが、シカのもも肉は350円/100g程度で手に入る。
シカ肉は火を入れすぎると硬くなりやすいので、多少扱いは違うが、適切に処理された肉なら臭みも少なく、意外と手軽に食べられる。
ミンチ肉だともっとお手頃だ。
一部スーパーでは、牛肉、豚肉、鶏肉とならんで、ジビエの棚がある。
たとえば、マックスバリュ九州の福岡県内の店舗では、精肉コーナーにイノシシ肉が並ぶ。
豚肉よりは高めの設定だが、売り切れることもある人気商品。
バイヤーさんがイノシシ肉の確保に奔走しているそうだ。
ジビエの生食は厳禁
国内では、シカ生肉を食したことでE型肝炎を発症した事例がある。
生シカ肉を介するE型肝炎ウイルス食中毒事例について – 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/08/h0801-4a.html
生食のリスクはよく知られているとは思うが、今でも特にシカは生食がされることがある。
筆者は食したことはないが、やはり、シカ生肉は美味しいらしい。リスクは承知で食べる人もいる。
2017年には80代の女性が輸血を受けた際にE肝炎ウイルスに感染。抗がん剤を投与中だった女性は、劇症肝炎になり亡くなってしまった。
その献血者は、生鹿肉を食べた方でE肝炎ウイルスに感染していたが、肝炎を発症していなかった。
E型肝炎ウイルスは体内にとどまるのは一時的で、肝炎を発症しても一時的で軽症なこと多く治療が可能ではあるが、寄生虫による食中毒リスクもある。
生食厳禁が基本。
だからといって獣肉が危険なのではない。火を通せば全く心配なく、美味しく食べられる。
ジビエの栄養素
ジビエは低カロリー、高たんぱく質。
シカ肉には多量の鉄分が含まれる。
イノシシ肉もシカには及ばないが、牛肉よりも鉄分が多い。
今、アスリートにも人気の食材だ。
脂肪燃焼を促すアセチルカルニチン
カルニチンは、脳機能の向上・ストレスの軽減の効果も
ジビエはアンセリンのような疲労回復成分、ダイエット
鉄分ホルモン剤なし、ミネラル成分が違う可能性
アンセリンは、抗酸化作用、疲労回復、持久力向上、アンチエイジングに関与すると言われる。
参照:農林水産省広報誌あふ
http://www.maff.go.jp/j/pr/aff/1801/pdf/1801_03.pdf
福岡県農業総合試験場「うまみ成分に富んだイノシシの解体処理及び熟成方法について」
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/64.pdf
一般に、牛や豚は粗飼料(牧草や稲わら)に加え、濃厚飼料(コーンなど穀物)を与える。
早く育てて、早く出荷するためだ。
現状、畜産業の経営環境は厳しい。効率化を追求する必要がある。
一方、野生鳥獣は自然の中でゆっくり育つ。そのためカルニチンやアンセリンといった成分が蓄積するのだろうか。
これは全くの私の想像でしかないが。
植物は化成肥料や適温下で早く育てた野菜よりも、ゆっくり育った野菜のほうが甘みが強かったり、栄養がたかったりする。
ジビエは食糧自給率の向上につながる。
ジビエを食すことは食糧自給率の向上、エネルギーの節約につながる。また、最小の素材でも継続できる。
現在、国産の牛肉、豚肉、鶏肉を購入されている方は、肉類は国内でかなり賄われている、と感じるかもしれない。
しかし、その牛・豚・鶏たちを飼育するエサはほとんどが輸入品である。
平成29年度の飼料自給率は26%。
国内全体の自給率は40%前後だから、国産のお肉を食べたからといって自給率が高まるわけではない。
一方、野生鳥獣であるジビエは、国内の野山でエサを食べており純粋国産だ。
輸入飼料を国内に入れるには、北米・南米などから運ぶためのエネルギーも必要だ。
国産ジビエであれば、そんなエネルギーもかからない。
また、罠猟であれば、スプリング・ワイヤーといった金属は必要だが繰り返し使える。
資源を節約できる猟法と言える。
狩猟者が捕獲獣や罠を運搬するために軽トラを走らせ、そこにガソリンは必要だが、畜産にも飼料の生産・運搬にトラクター等を使うので、そこはイーブンでよいのでないだろうか。
有害鳥獣対策・ジビエ振興のIOT化
今後少ない狩猟者で増え続ける野生鳥獣の個体数管理(駆除)をする必要がある。
現在、あらゆるものがインターネットとつながる(IoT化)時代だ。
そんな中、罠のIoT化も進みつつある。
箱罠やくくり罠がインターネットにつながり、捕獲状況を狩猟者に通知する。
捕獲された野生獣も苦しむ時間が短くて済む。
獣にもよいし、苦しむ時間が短い分、肉質も良くなりやすい。
ジビエとしての利用率が高まる。
また、どの山林で、いつ捕獲され、いつ処理されたか、そんな情報をトレースことも可能だ。
導入コスト、ランニングコストは検討する必要があり、簡単ではないが。
ジビエが第4の肉になる日
いつか牛・豚・鶏とならんで、イノシシやシカ肉がもっとポピュラーになればと思う。
一般家庭で、「今日はシカにしよっか」と普通になる日。
狩猟者が活躍し、
野生鳥獣との共存ができ、農山村で農業を継続できる未来。
ジビエの消費が増え、理想を言えば補助金なくビジネスになればと思う。
現状ではそんな理想が実現するとは想像できないが、ウォルト・ディズニー、本田宗一郎さん、松下幸之助さんなどが不可能を可能にしてきた。
理想は理想として描いても良いのではと思う。
農林業の有害鳥獣対策を根幹としてジビエ振興がより進みますように。
陰ながら応援したい。